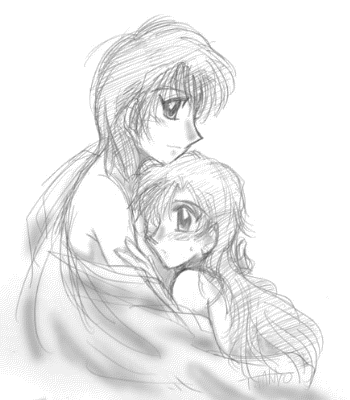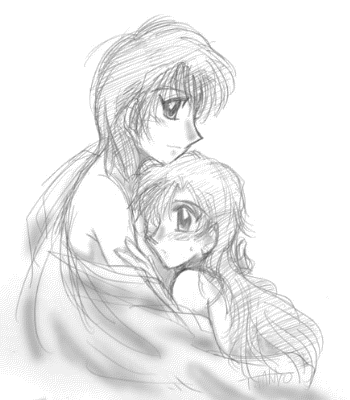† 追憶(仮) †
深森 薫
寝起きの体を温めの湯に浸すのが、マーキュリーの日課だった。
八分目まで湯を張ったバスタブにミントの香料を加え、そこに肩まで浸かって深呼吸を一つ二つ。脳細胞を刺激し覚醒をもたらす清冽な香り。心地よい温度は停滞していた血液の循環を活発にし、体中の細胞が目を覚まして動き出す。湯船の中でうんっ、と背伸びをすると、指先から足の爪先まで、体中に酸素が取り込まれていくようで。ゆっくり手足を動かすと、かき混ぜられた湯からミントの香りが一層強く立ちのぼる。
申し分ない、一日の始まり。
そうは言っても朝からあまり長湯するわけにもいかない。もうひとしきり朝湯を楽しんだところで、彼女は湯船から立ち上がった。
バスローブを羽織り、緩やかなウエーブをかたどる長い髪をタオルで挟むように拭う。アイボリーのバスローブは彼女には大きすぎるようで、肩が随分余って胸元の開きも広い。長い袖を少々邪魔に思いつつ、手早く乾かした髪を慣れた手つきで、丁寧に編み込んでいく。そうこうしているうちに昨夜脱ぎ散らかした服のプレスも出来上がり、すっかり身支度が整った。
−−−完璧。
朝帰り出勤には、まず見えない。
鏡で後ろ姿まで念入りに確かめて、彼女はバスルームを出た。
明かりの落ちた静かな居間。扉の向こうからは、一日の営みを始めた人々の活気が遠いさざめきのように聞こえてくる。
この室の主は、まだ夢の中。
彼女はソファーの上に放り出された書類ケースを取り上げ、一度はこの部屋を出ようとしたが、後ろ髪を引かれるように寝室のドアに手を掛けた。
少しだけ開いた隙間に体を滑り込ませ、癖のあるドアを後ろ手に、静かに閉める。強い朝陽が閉め切ったカーテンの裾からわずかに漏れて、部屋全体をほんのりと照らしている。広さの割には物の少ないがらんとした室内の、真ん中より少し奥にベッド。彼女は足音をたてないようにゆっくりと近付くと、そこにあった寝顔を覗き込んだ。
「・・・ジュピター・・・?」
呼ばれた名前の主の、返事はない。
整った、彫りの深い顔立ちに伸びかけたショートの黒髪。子どものように両腕をシーツの上に投げ出して、穏やかな寝息をたてながら上掛けに半分隠れた胸を規則正しく上下させている。創世神話に登場する美青年やと見まごう容貌だが、首から腕にかけてのラインと緩やかな胸の隆起は男性のものではなかった。そもそも、月王家の近衛である『守護神』に男が選ばれることはあり得ない。
(・・・・・・ふふっ)
彼女は愛おしげに笑って眠る人の額にかかる黒髪を払うと、剥き出しの肩を覆うようにそっと上掛けを引き上げた。
と。
突然その手を掴まれたかと思うと、
「−−−!」
声を上げる間もなく、彼女の身体はシーツの上に投げ出されていた長い腕に抱き留められていた。
「お早う」
耳元で、ふっと微かに笑う気配が囁きに混じる。
「・・・・・・もうっ、ジュピタっ−−−」
悪戯っ子を咎めるような眼差しを黒い瞳が捉え、その先の言葉を唇で遮った。
目覚めの挨拶にしては少し長いキスの後。
互いの吐息の感じられる微妙な距離で、再び視線が絡み合う。
「で?」
ジュピターが、からかうような笑みを浮かべた。
「何処に行くんだ、そんな恰好で」
「そんな恰好、って」
守護神の略正装、いわゆる普段着である。
「勤務に、決まってるじゃない」
「勤務、ねぇ」
にやにやと笑ったまま、指先はマーキュリーの顎から頬のラインをゆっくりとなぞり、耳元の後れ毛をくるくると弄ぶ。
「そんなに好きなのか? 仕事」
「好きとか嫌いとか、いう問題じゃないと思うんだけど」
呆れたように答えるマーキュリー。
「ふうん・・・・・・じゃあ」
ジュピターの手が止まる。
新しい悪戯を思いついた子どものように、顔がほころび。
「サボっちまえ」
「え? っ!」
言うが早いかくるりと体を翻し、あっという間に彼女をベッドに組み敷いた。
「ちょっ、なっ、何考えてるのっ・・・」
抗議の声を封じるように、唇を重ね。
深く、口づける。
「んっ・・・・・・駄っ、目・・・だって、ば」
次第に荒くなる呼吸の隙間から、それでもささやかな抵抗の言葉を絞り出すマーキュリー。
「どうして? こういう時のための、優秀なスタッフだろう」
ジュピターは不敵な笑みも顔色も変えずに囁く。
耳元で、わざと吐息混じりに。
「上官は後から悠々と登場すればいいのさ。首にキスマークの一つも付けてな」
「キっ・・・!」
マーキュリーの身もがく力が少し強くなる。
「駄目っ、それじゃ、皆に示しがつかない−−−」
「皆だって示しをつけなきゃならんほど子どもでもあるまい」
そう囁く声が、重ねた頬を震わせる。
「生真面目だな」
「あなたが不真面目なのよ・・・とっ、とにかく、首にキスマークなんてっ」
「そうか・・・」
大仰に溜息をつくジュピター。
マーキュリーが安堵の笑みを浮かべた。
そして、それを待っていたかのように。
「・・・じゃあ、首じゃなきゃいいんだな?」
ジュピターはしてやったりと言わんばかりに不敵に笑い。
今一度、唇を重ねる。
滑るように、割り込む舌。
それは貪るような淫らな音をたてて、絡みつき、口腔を縦横に愛撫する。
先刻までのそれとは比べものにならない、本気のキス。
与えられる柔らかな快感に、白濁する意識。
呼び起こされる、重ねた肌の記憶。
活動を始めた巨大な生き物のような王宮の中、まだ薄暗い室内はそこだけ切り取られたような静けさを保っていた。次第に加速する吐息の下、聞こえるのは繰り返す接吻とシーツの衣擦れの音。
やがてその中に艶を帯びた声が混じり始めるまで、さほど時間はかからなかった。
「ねえ、ジュピター・・・・・・」
ジュピターの胸に顔を埋めたままのマーキュリーは、まだ何処かぼんやりとしたように口を開いた。ん、と応えるジュピターの、左腕は彼女の腰を抱きかかえ、右手は長い髪を梳く流れるような動作を繰り返している。
「・・・・・・そろそろ・・・・・・行かなきゃ、私」
そう言って、マーキュリーはジュピターの腕からするりと抜けて身を起こすと、先刻まで身に着けていた布を拾い上げて再び身に纏った。
ジュピターはやはり『ん』とだけ応えて、ただ彼女の様子を眺めている。
「髪。結い直さなきゃ・・・結構、時間かかったのよ?」
マーキュリーは解けた髪を手櫛で簡単に束ねると、少し非難がましく聞こえるようにそう言った。
「いいじゃないか。その方がずっと、そそられる・・・もっとも、いつものいかにもお堅い感じも十分そそるがな」
ジュピターは喉の奥でくくっ、と笑って切り返す。
朱がさした頬を隠すように、マーキュリーは背中を向けた。
「今日は・・・どうするの、これから」
やがて、彼女が振り向きながら訊ね。
「・・・・・・ここに居る」
ジュピターは背伸び一つして、気怠そうに答えた。
「ずっと?」
「今日は、お前以外の人間と話すのがめんどくさい」
頭の後ろで手を組んで、枕に背中を沈めて。
「もうひと寝入りして、何か食って・・・
お呼びが掛かれば、出て行くさ」
「・・・そう」
マーキュリーがくすりと笑った。
「何」
「なんだか、聞き分けのない駄々っ子みたい」
「子どもに子どもだなんて言われちゃ、心外だな」
「あら。そのお子様にご執心なのはどこの誰?」
「・・・・・・可愛くないことを言う」
「意地悪は誰かさんの直伝だもの」
鼻白むジュピターの様子に、マーキュリーはまたくすりと笑い。
「じゃあ。そろそろ、本当に行かなくちゃ」
そう言って踵を返した。
「キュリー」
その背中を、ジュピターが呼び止める。この王宮で彼女をそう呼ぶのは、ジュピターを除いて他にはいない。
「なに?」
振り返った彼女に、ジュピターが手招きをする。
「・・・また変なこと考えてるんじゃ、ないでしょうね?」
「疑り深い奴だな」
ジュピターは苦笑いして、彼女に向かって促すように手を差し伸べた。
「普段の行いよ」
ベッドサイドに立ったマーキュリーが、促されるまま枕元にかがみ込んでそっと唇を重ね。
触れるだけのキスを解いて離れようとするのを、ジュピターが引き寄せた。
「キュリー」
優しい力で抱き締めて、
「・・・愛してる」
耳元に口を寄せて、表情は見せずに呟く。
私も、と小さな声で答えて、彼女は体を離した。
「・・・じゃあ・・・・・・また、後でね」
そう言って部屋を出ていくマーキュリーに、軽く手を振って応え。
長い溜息をついて、ジュピターは再び羽枕に肩を沈めた。
部屋の扉の向こうでは、いつもと変わらぬ日常が始まっている。
ただ。
今日だけは、その中に出ていく気がどうしても起きなくて。
独り、薄闇の中で眼を閉じた。
−−−追憶(仮)・終
|